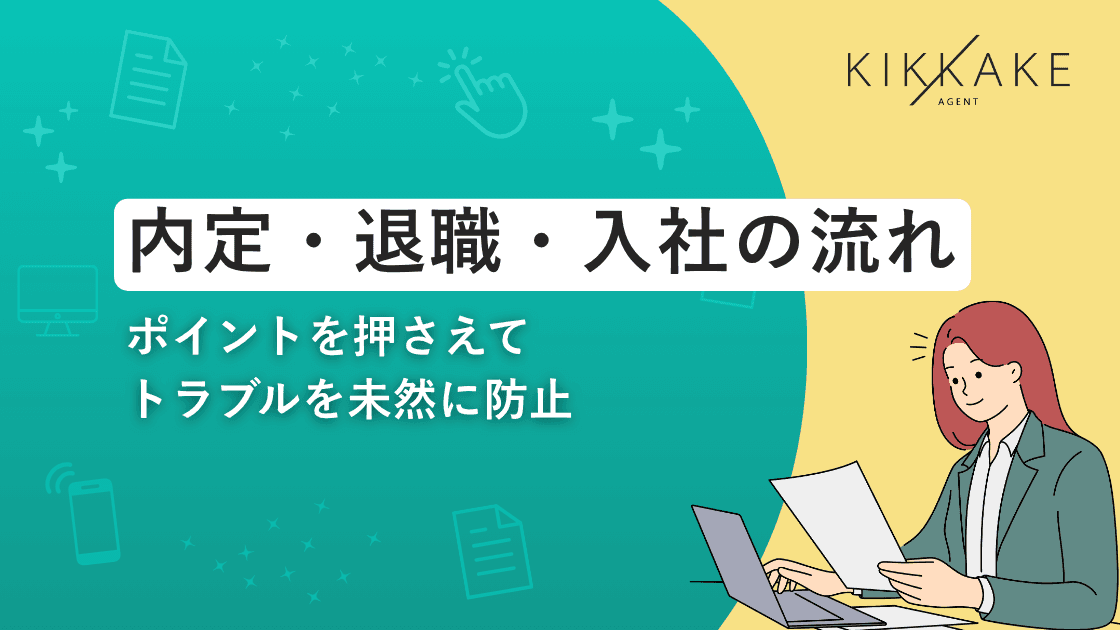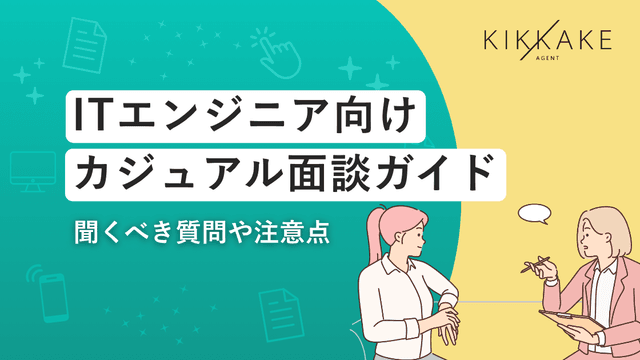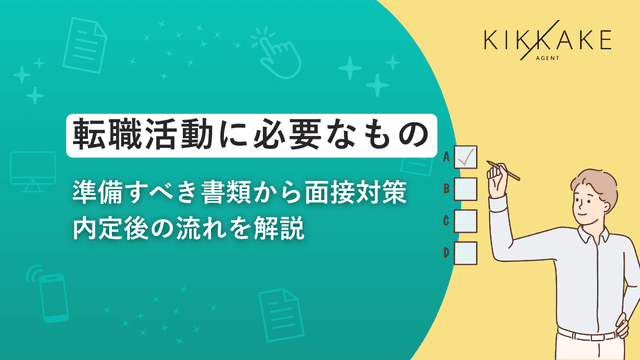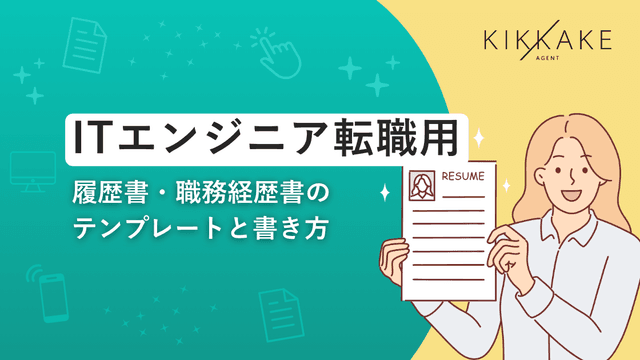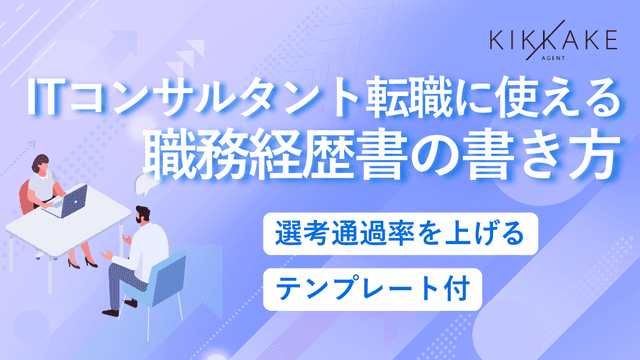転職活動を経て内定獲得の喜びも束の間、退職や入社に向けた準備が始まります。上長との交渉や同僚への引継ぎ、保険や税金に関わる手続きなど、やるべきことは山ほどあり、カオスになりがちなのがこの時期です。抜けモレなく必要なタスクを完了させるためには前もって段取りしておくことが大切といえるでしょう。
ここでは、内定から退職、入社までの流れを完全ガイドします。この記事の内容をしっかりと把握しておけば、やるべきことに忙殺されることなく、ストレスを減らしてスムーズなスタートを切れるはずです。是非参考にしてみてください。
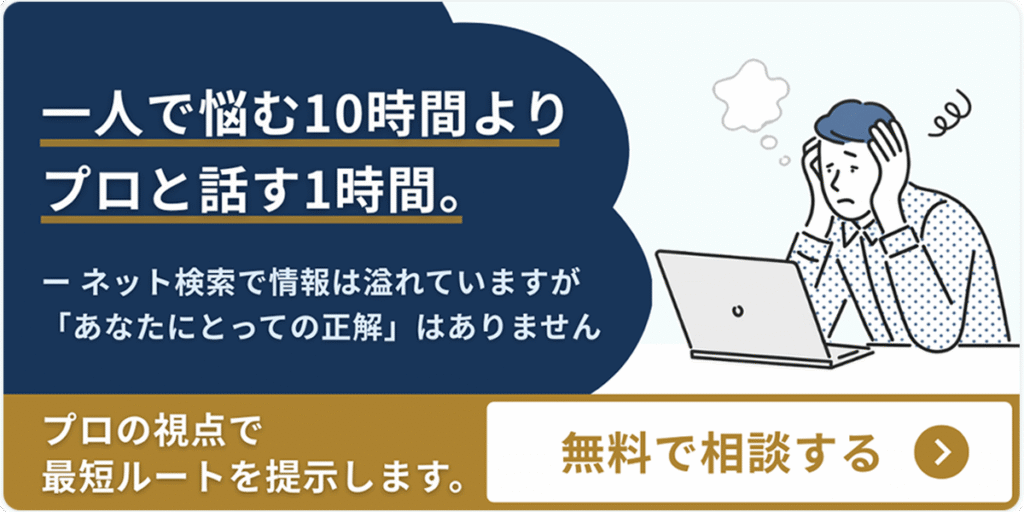
内定から退職までの大まかな流れ

内定から退職までの大まかな流れは以下の通りです。民法では、退職日の2週間前に申し入れをすれば使用者の承諾がなくても退職が可能としています。ただ、労働契約や就業規則が民法と異なる定めをした場合には、その定めが優先されることになります。つまり、合理的な理由があれば、この期間を延長することが可能ということです。
一般的には、管理者クラスであっても引継ぎを含めて、内定から退職までは2~3カ月と考えておけばよいでしょう。もし、内定が決まってから「半年はほしい」と使用者側から言われるようなら、労働者の退職の自由が制限されることになるため、公序良俗の見地から無効とされる可能性があります。
| 内定から退職までの流れ |
|---|
| 内定 ↓ 退職の意思表示 ↓ 退職日の相談 ↓ 退職届 ↓ 引継ぎ ↓ 退職 |
以下では、それぞれのステップをさらに細かく分けて、注意すべきポイントやよくある質問に対する答えについて解説します。
内定

内定連絡を受ける
内定連絡は電話やメール、あるいは書面の郵送にて通知されます。内定連絡を受けたら、早め(当日もしくは遅くとも翌日中)に連絡しましょう。企業側から指定がない限り、原則として電話で回答するのが望ましいです。電話で伝えるべきことは、選考結果のお礼と、内定の「承諾するのか、辞退するのか、あるいは保留にするのか」の意思表示です。
第一志望の企業から内定通知が来たら、嬉しくてすぐにでも承諾の返事をしたいと思うかもしれません。しかし、まずはひと呼吸置きましょう。内定の承諾は雇用条件を確認してからです。通常は内定通知と同時に雇用条件が提示されます。のちほど遅れて提示される場合は、いつ、どのように雇用条件が届くか明示されますので、それを待ちましょう。
雇用条件の再確認
雇用条件で確認したい事項は以下の通りです。面接の際に提示された条件と異なるように思えたり、不安を感じたりする点が少しでもあれば、採用担当者に確認しましょう。
雇用条件で確認したい事項
- 入社日
- 契約期間(有期雇用の場合は更新基準も)
- 試用期間
- 就業場所
- 業務内容
- 労働時間(士業就業時間・残業の有無・休憩時間・休日休暇)
- 賃金(基本賃金・諸手当・賞与・割増賃金・締切日・支払日・支払方法)
- 昇給(昇給の有無・昇給条件)
- 退職(定年制度・継続雇用制度・退職金)
厚生労働省が作成した労働条件通知書の見本もチェックしておくことがおすすめです。
家族に連絡
内定承諾前に家族の意向を確認しておきます。というのも、エンジニアである本人にとって魅力的でやりがいがある仕事のように感じても、家族の考えは異なるケースが多々あるからです。
家族とのコミュニケーションが不足したまま内定を承諾してしまうと、あとでトラブルになる可能性が高いでしょう。最悪の場合、内定を承諾したあとに家族に引き留められ、最終的に辞退せざるを得なくなるケースも考えられます。そうなると、受け入れ準備を始めている企業側にも迷惑をかけることになってしまいます。
内定承諾
内定通知に対してすでに内定を受け入れる意思を表明していても、後日「内定承諾書」や「入社誓約書」など正式な書面に署名し、提出を求められる場合がほとんどです。「内定承諾書」などの書類を提出したとしても、法的には入社2週間前までならいつでも入社辞退が可能という点も覚えておきましょう。
ここで、内定承諾時・内定保留時・内定辞退時のメールのテンプレートをご紹介します。先述したように、内定受諾の返事については基本的には電話が望ましいですが、相手企業側からメールで通知を受けた場合は同じようにメールで返信しても失礼にはなりません。その場合には、以下のテンプレートをご活用ください。
内定承諾のテンプレート
| 株式会社〇〇 〇〇部 採用担当 〇〇様 お世話になっております。〇〇です。この度は貴社より内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 貴社のビジョンに非常に共感しており、内定のお話をいただけたことを大変嬉しく思います。貴社の内定をありがたくお受けさせていただきます。 今後、貴社の一員としてエンジニアとして成長し、貴社の発展に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。入社日や必要な手続きなど、今後の流れにつきましては、引き続きご指導賜りますようお願い申し上げます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 |
内定保留のテンプレート
| 株式会社〇〇 〇〇部 採用担当 〇〇様 お世話になっております。〇〇です。 この度は、貴社より内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 貴社の魅力的なビジョンや技術力に感銘を受けております。内定のお話をいただけたことに、心より感謝申し上げます。 すぐにでもお返事をさせていただきたいのですが、重要な決定であるため、もう少し検討する時間をいただきたく存じます。現在、他の選考状況や自身のキャリアの方向性について慎重に考えており、誠に恐れ入りますが、〇〇日までお時間を頂戴できれば幸いです。 貴社にご迷惑をおかけすることなく、最善の決定をしたいと考えておりますので、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 |
内定辞退のテンプレート
| 株式会社〇〇 〇〇部 採用担当 〇〇様 お世話になっております。〇〇です。 この度は、貴社より内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 貴社のビジョンや事業内容に大変魅力を感じ、内定をいただいたことに心より感謝しております。しかし、誠に勝手ながら他の企業にてキャリアを進めることを決断いたしましたため、貴社からの内定を辞退させていただきたく、ご連絡させていただきました。 貴社にご期待をいただきながら、このようなご連絡を差し上げることは大変心苦しい限りですが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 最後になりましたが、貴社のますますのご発展と、貴社の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 |
今後の予定の調整
内定を承諾したら、現在就業中の会社の人事担当者と今後の退職交渉、転職先の人事担当者と入社予定日の調整に入ります。上述したように、内定から入社までは引継ぎを含めても長くて3カ月程度と考えておきましょう。
さまざまな事情が関係しますが、退職日は転職する企業の入社日前日にすることが理想です。なぜなら、退職日と入社日の間が1日でも空いてしまうと、健康保険や国民年金などの社会保険手続きが発生し、手続きを自ら行わなければならないからです。
内定トラブルQ&A
ここでは、内定でよくある3つのトラブルについて取り上げます。
Q:内定を取り消されたら?
A:企業が一方的に内定を取り消すことができるのは、採用内定通知書などで規定されている取消原因に含まれ、かつ客観的に合理的であり社会通念上相当である場合に限ります。
そのため、一方的に企業側から内定取消を通知されたら、まず理由を説明してもらうようにお願いしましょう。不当な内定取消の場合は賃金や損害賠償を請求できることもありますが、だからといっていきなり対決姿勢にならないようにすることも大切です。
もし、内定取消の合理的説明を求めてもきちんとした回答が得られなければ、相手企業の言いなりになって内定取消の同意書にサインする前に、労働基準監督署の相談コーナーなどに相談することをおすすめします。
Q:内定辞退を強要されたら?
A:内定辞退を強要される場合、はっきりと断ることが可能です。ただ、内定辞退を強要するような状態ですでに企業側と信頼関係を構築することが難しいと感じれば、補償を請求した上で内定を辞退することもできるでしょう。
いずれにしても一人で企業側と交渉するよりも、まずは労働基準監督署に相談したり、あっせん手続きを活用したりすると良いでしょう。
Q:内定は辞退できるのか?
A:入社の2週間前までであれば、内定承諾書の提出後に辞退しても法的には問題ありません。ただ、法的に問題はないといっても、一般的に内定後、企業は内定者の受け入れのためにポジションを整えたり、備品を購入したり準備を進めています。内定を辞退する場合には企業側に極力迷惑をかけないよう、速やかに意思表示しましょう。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談する退職の意思表示

退職の意思表示をするときは、上長に対して「相談があります」というスタンスではなく、決定事項として伝えるようにします。
退職の意思表示の仕方ですが、ドラマで見るような紙での「退職願」は必ずしも必要ありません。電子的に退職の意思表示をする場合は、消去できてしまうLINEなどでのメッセージではなく、消去できない電子メールで伝えると良いでしょう。
退職日の相談

法的に2週間後には退職できるといっても現実的にそれは難しいでしょう。円満な退職のためには、上長と退職日の相談をする必要があります。上述したように部長など管理者クラスの場合でも「長くて3カ月」を目安に調整しましょう。
退職者側からすれば、自分の直属の上長だけでなく、人事担当者などさまざまなポジションの人に声をかけておかなければと思うかもしれません。しかし、自分からそうする義務があるわけではありません。
覚えておいていただきたいのは、自分が希望した日に退職できる権利があるということ。退職日は「相談」はできるものの、相手が「強制」することはできないということです。
退職が遅れて、入社が当初の予定より長引いてしまうと何かとデメリットがあります。受け入れる企業側の視点から見れば、あなたが入社することを前提にチームを編成したり、仕事内容を調整したりしてくれているはずです。例えば、当初の通り入社できていれば、そのプロジェクトの要件定義の工程から関わることができたのに、入社が遅れたばかりに携われなくなってしまうこともありえます。
また、入社時期が遅れると、想定年収や賞与も当初提示された額より少なくなることも考えられます。必要以上に気を遣って上長の言われるがままに退職日を設定することは、自らの機会損失につながることも覚えておきましょう。
引継ぎ

引継ぎ業務は多岐に渡ります。ポジションや業務内容によって内容も変わってきますが、例えば以下のようなものが考えられます。
- 担当業務の流れをフローチャートにまとめる
- 各工程の注意点、優先順位、作業手順を可視化する
- 顧客企業や担当者リスト
- 業務連絡先一覧
- 業務ごと、取引先ごとに起きやすいトラブルと対処法
- 社内資料や書類、帳簿類などの保管場所
業務内容にもよりますが、引継ぎの項目は膨大になります。無計画に漫然と進めていてはあっという間に時間が足りなくなってしまいますし、他のメンバーとの連携もうまくいきません。そのため、最初にすべきことは、スケジュールを立てて引継ぎすべきことを可視化することです。
また、退職前に有給休暇を消化しておきたいと思うでしょうし、それは労働者の権利でもあります。しかし、引継ぎが完了する前に退職日を迎えることがないよう、有給休暇も計画的に取得するようにしましょう。遅くても退職日の2~3日前までには引継ぎを完了できるよう、余裕を持ってスケジュールを組むようにしたいところです。
後任者へ引継ぐ際は、口頭のみではなく、担当業務のやり方や流れをまとめたマニュアルを作成しておきます。自分が退職したのち、トラブルが発生しても後任者が速やかに対処してミスせずに済むよう、注意すべきポイントを記載しておくとより親切です。
引継ぎ期間は通常2~3カ月ですが、その前半を後任者とともに業務を行い、後半は実際に後任者に任せて見守る期間を設けると良いでしょう。後任者も実際に自分でやってみることでいろんな疑問を明確にして、それを解消することができるからです。
社内外へ退職の挨拶メールを送る際、後任者も紹介しましょう。退職直前は避け、2~3週間前には送付するようにします。送付するタイミングは上長とも相談したうえで決めるとよいでしょう。挨拶状の例文は以下の通りです。
| 社外向け 退職挨拶メール例文(訪問なしの場合) |
|---|
| 件名:退職のご挨拶と後任者のご紹介 〇〇様 いつも大変お世話になっております。 〇〇です。 この度、〇〇年〇〇月〇〇日をもちまして、〇〇株式会社を退職する運びとなりました。最終出社日は〇〇月〇〇日の予定です。 本来でしたら直接ご挨拶させていただくべきところ、メールでのご連絡となり大変申し訳なく存じます。在職中は〇〇様はじめ貴社の皆様にご厚情を賜り、誠にありがとうございました。 私の退職に伴い、今後の担当は【後任者の名前】が引き継がせていただきます。【後任者の名前】は、〇〇に精通しており、皆様のご期待に十分お応えできるものと確信しております。何かご不明な点やご要望がございましたら、遠慮なく【後任者の名前】にご連絡いただければと思います。 改めて【後任者の名前】がご挨拶に伺いますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【後任者の名前】の連絡先は以下の通りです。 メール:〇〇@〇〇.com 電話番号:〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 末筆ながら、皆様の益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。 (署名) |
貸与物の返却
退職時に、会社から貸与されていたものや、自分が社員であることを証明するもの、社費で購入したものなどは返却しなければなりません。特に会社から貸与し、業務で使用していた端末は返却しなければ情報漏洩につながる可能性があるため、十分注意しましょう。
退職時の業務内容やポジションによって返却物は異なりますが、例えば以下のようなものがあります。
- 身分証明書(社員証)・社章
- 名刺
- 健康保険証
- 通勤定期券
- 貸与されていた端末、備品、書籍 など
必要書類の受け取り
必ず受け取るべき書類は、「雇用保険被保険者証」「年金手帳(基礎年金番号通知書)」「源泉徴収票」です。
必要に応じて受け取る書類には「離職票」「退職証明書」「厚生年金基金加入員証」などがあります。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、自らが雇用保険の加入者であることを証明する書類です。一般的には会社で保管されているため、退職時には雇用保険被保険者証を受け取り、新しく入社する会社に提出する必要があります。
年金手帳(基礎年金番号通知書)
年金手帳とは、「国民年金や厚生年金の被保険者であることを証明する手帳」です。20歳以上であれば、必ず保有しているはずです。基礎年金番号を確認するだけのため、入社時に提出し、コピーを会社が保管していることもあります。もし、手元になければ会社が管理していますので、退職時には受け取りましょう。
なお、令和4年4月からは冊子の年金手帳は廃止され、基礎年金番号通知書を発行する形に変更されています。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、その年に会社から支払われた給与などの合計と、そこから天引きされた所得税の金額が記載された書類です。転職先の会社が年末調整を行う際に必要になるため、必ず受け取りましょう。
離職票
離職票とは、退職した事実を証明する書類で、退職後にハローワークで失業保険給付を行う際に必要になります。そのため、退職後の転職先が決まっている場合は基本的に必要ありません。
退職証明書
退職証明書とは、退職したことを証明する書類で、転職先の企業で提出を求められることがあります。また、転職先への入社までに時間が空くなどの際、国民健康保険や国民年金の手続きで必要になる書類です。
厚生年金基金加入員証
厚生年金基金加入員証は、会社が厚生年金基金に加入している場合にのみ、退職時に返却されます。多くの場合、年金手帳と合わせて手続きが行われます。受け取り時には書類の情報に誤りがないかを確認しておきましょう。
デスクやロッカーの整理
長年使用したデスクやロッカーは感謝の気持ちを込めて清掃、整理しましょう。
退職

昨今、メディアなどでも話題になっている「退職代行」ですが、よほどのことがない限り、使わないほうが良いでしょう。
なぜなら、企業によっては採用時のリファレンスチェックを重視しているところも多いからです。リファレンスチェックとは、人材採用の際に前職・現職の上司や同僚にヒアリングして転職者の勤務状況などをチェックすることです。そのため、退職代行サービスを利用したことが知られ、ネガティブな印象を持たれる可能性もあります。
税金・保険の手続き
退職後にすべき税金・保険関係の手続きは主に5つです。基本的には以下の順番で行います。
①住民税の支払い
住民税は1~12月の所得に対して、翌年6月~翌々年5月に渡って納めます。退職後、1カ月程度で転職する場合は入社後に毎月の給料から天引きされるため、自分で支払い手続きをする必要はありません。
退職後から次の転職まで1カ月以上ある場合、1~5月に退職する場合は手続きは不要です。6~12月に退職する場合は、最後の給与から翌年5月分までの住民税を一括天引きする手続きが必要になるため、事前に担当者に伝えておきます。一括天引きされない場合は、普通徴収に切り替わり、3カ月ごとに自分で納付することになります。
②失業保険の申請
退職後、すぐに転職する場合は必要ありませんが、一定期間転職活動を続ける場合は失業保険の申請が必要になります。上述した離職票が届き次第、すぐにハローワークで手続きしましょう。
③年金手続き
退職後、すぐに転職する場合は基礎年金番号かマイナンバーを伝えれば特段の手続きは必要ありません。ただ、退職から転職まで失業期間がある場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。その場合、退職から14日以内に役所での手続きを行いましょう。
④健康保険の切り替え
退職後、すぐに転職する場合は入社する会社で保険証を発行してもらいます。新しい保険証の発行まで1~3週間程度かかるため、この期間中の医療に関しては「健康保険被保険者資格証明書」を担当者に作成してもらって受け取り、医療機関に提出しましょう。
⑤確定申告
確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算して申告する手続きです。退職後、年内に転職しなかった場合には確定申告が必要になるため、忘れずに行いましょう。
退職トラブルQ&A
Q:退職の意思表示を聞いてもらえず、引き留められたら?
A:退職の期日は自分で決めることができます。その上でメールで上長に送るなり、テキストでのエビデンスを残すようにしましょう。そして、退職の意志は揺るがないことを言葉で伝えます。
また、引き留められて年収アップなどを口約束で提示されても、安易には信じないようにしましょう。多くの場合、将来予定されている昇給が前倒しになっただけで、退職予定者にとって特段のメリットがあるわけではないケースもあります。
それでも、提示された条件に興味があるようなら、「〇月〇日まで〇円昇給する」といった具体的な約束を電子メールなどのテキストにて送ってもらうようにします。
Q:損害賠償を請求するといわれたら?
A:「損害賠償を請求する」とプレッシャーをかけられることはあるものの、実際にそのようなケースに至ることはまれです。
この点で多くの方が気にするのは「競業避止義務」かもしれません。「競業避止義務」とは例えば「2年間は同業他社では勤務できない」というような規定です。ただ、現場のリーダーやマネージャーが競業避止義務に抵触することはほとんどありません。高度な機密情報を把握している役員レベルであれば気にする必要があるかもしれませんが、「競業避止義務」を遵守する代わりに「代替措置」(例えば、「2年間は同業他社に転職しない代わりに500万円支払う」など)を設けることが求められています。
エンジニアに現場リーダー、マネージャーレベルの方であれば、「競業避止義務」についての書類に署名を求められても、穏やか、かつきっぱりと断るようにしましょう。
Q:有給の取得申請の許可がおりない場合はどうしたら良い?
A:有給取得は労働基準法で保障されている労働者の権利です。そのため、相談しても頑固に拒まれる場合は、メールなどで「いつからいつまで有給取得する」旨を伝えた上で有給に入るのも一つの手段です。ただ、こうしたケースでは企業側とのコミュニケーションが困難な場合も少なくないため、困ったら転職エージェントに相談するのもありでしょう。
Q:貸与物の返却は郵送でもよい?
A:どうしても直接渡せない場合は会社に早めに連絡し、郵送することも可能です。健康保険証は一般書留か簡易書留で送り、対面で受け取ってもらえるようにしましょう。特に一般書留は郵便物を出してから届くまで経由した郵便局や配達時間が細かく記録されるため、安心です。
Q:退職後に書類が届かなかったら?
A:退職後、離職票などの必要書類が届かない場合、まずは前職の担当者にメールで連絡し、そのあと電話で状況確認しましょう。離職票が届かない場合、失業給付を受け取れない可能性があります。急ぎで送ってもらうように再依頼しましょう。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談する入社

円満に前職を退職したら、いよいよ転職先に入社です。ここからは入社前にしておくべきことや、新しい環境でエンジニアとしてハイパフォーマンスを発揮するために入社当日、入社後に心がけたい点についてご紹介します。
入社準備
書類の準備
入社にあたって必要な書類は会社側から指定されるため、基本的にはそれに従って提出すれば良いでしょう。一般的には退職時に受け取っているはずの「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」は入社手続きにおいても必ず必要です。
自己紹介文を準備
転職初日に自己紹介が求められる機会があるはずです。第一印象がすべてを決めるわけではありませんが、転職後の人間関係構築においても重要なタイミングです。名前だけでなく、所属や前職でどんなプロジェクトに関わっていたかなど、伝えたい内容を簡潔にまとめておきましょう。
キャリアの強みを前面に推し出すよりは、新しいフィールドで自分の経験やスキルを役立てていきたいという謙虚な姿勢が好印象につながります。
| 自己紹介文の例 |
|---|
| はじめまして、〇〇と申します。エンジニアとして、〇年以上の経験を積んでまいりました。主に【Python】を用いた開発を得意としており、【具体的なプロジェクトや業務内容】に従事してきました。 これまでに、【システムの改善、アプリケーションの開発、業務効率の向上】を目指し、チームでの開発や、顧客とのコミュニケーションを行ってきました。 現在は、【データ解析】にも関心があり、自己研鑽を続けながら、より高度な技術力を身につけ、さらなる成長を目指しています。 不慣れな点も多く、皆様にはご迷惑をおかけすると思いますが、一日でも早くお役に立てるように精進してまいります。 これからどうぞよろしくお願いいたします。 |
企業について理解しておく
入社後の研修などを通じて新しい会社の業務内容や沿革、経営方針などについて詳しく知っていくことになりますが、最低限の知識は会社のホームページなどを読み込み、理解しておきましょう。
資格取得
退職後、入社までの期間を利用して資格を取得しておくと、新しい企業に入社後、資格手当が出る可能性があります。特にAWS関連の難易度の高い資格はおすすめです。資格を取得していることで営業でも案件が取りやすくなります。
キッカケエージェントでは、転職を検討しているITエンジニア向けに、資格取得のための勉強会やイベントを定期的に実施しています。会員登録はこちらから。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談する入社当日
入社当日は心の余裕を持って、早すぎず、遅すぎない出社を目指します。第一印象を大切にし、準備した内容で自己紹介を行います。
入社後
すでに一定の経験やスキルがあったとしても、転職先のやり方やルールを理解することが先決です。エンジニアの仕事の多くはチームでのプロジェクトのため、他の社員との協力が欠かせませんし、転職先の上司もその点に注目しています。
できれば、最初の1カ月以内に同僚や上司、プロジェクトメンバーと一緒に食事をして交友を深めるようにしましょう。この機会を通じて、自分のキャラクターややる気を知ってもらいます。できれば、オフラインでの交友が理想です。フルリモートの場合でも入社時1カ月以内で食事会などの実施がないかを自分から聞いてみてはいかがでしょうか。そのようにして、自らの主体性をさりげなくアピールしていきましょう。
入社トラブルQ&A
Q:入社日に間に合わない。遅らせることは可能?
A:当然ですが、入社日は延期しないことが望ましいでしょう。特にエンジニアの場合、転職後にすでに進行中のプロジェクトを前提に入社日が設定されていることもあるからです。もし、入社後の業務に支障がない場合は入社日の延期を承認してもらえるかもしれませんが、万が一お願いするとしても1回までにしましょう。
Q:入社してからの勤務スケジュールを事前に確認してもよいのか?
A:問題ありません。内定後にやむを得ない所用が入ることが分かった時点で早めに共有しておくようにしましょう。
Q:有給消化中に転職先で働き始めることはできる?
A:前職の有給消化中に転職先で働き始めることができるかどうかは、就業規則上で二重就労が禁止されているかどうかによって決まります。もし、いずれの企業の就業規則にも抵触しないようなら、事情を説明し、二重就労の承認を得ましょう。
キッカケエージェントでは無料キャリア相談などを実施中。会員登録はこちらから。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談するまとめ

内定から退職、入社までの流れを解説しました。仕事をしながらの転職活動は予想以上にハードで、やるべきことはたくさんあります。また、人生のうちで何度もない転職活動期間。必要なポイントを押さえ、ストレスフリーで乗り切りましょう。
キッカケエージェントでは無料のキャリア相談を行っています。会員登録はこちらから。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談する関連動画
転職のミスマッチをゼロにする
キッカケエージェントは、あなたのオンリーワンのエンジニアキャリアを共創します
今の時点でご経験をされている言語や技術要素に関係なく、
① 技術を通じてユーザーやお客様にとって使いやすいサービスの実現に興味があるエンジニアの方
② 興味・関心がある技術について自ら学ぶ意欲をお持ちの方
上記に当てはまる方でしたら、素晴らしい企業とのマッチングをお手伝いできる可能性が高いです。
ITエンジニア転職のプロに
今すぐ無料で相談する